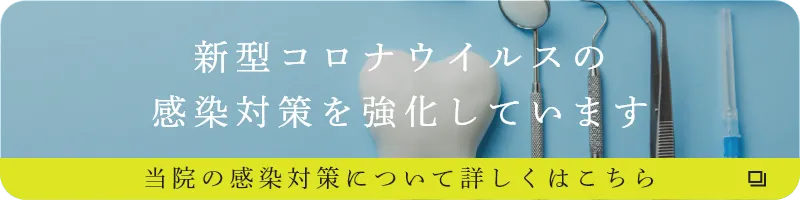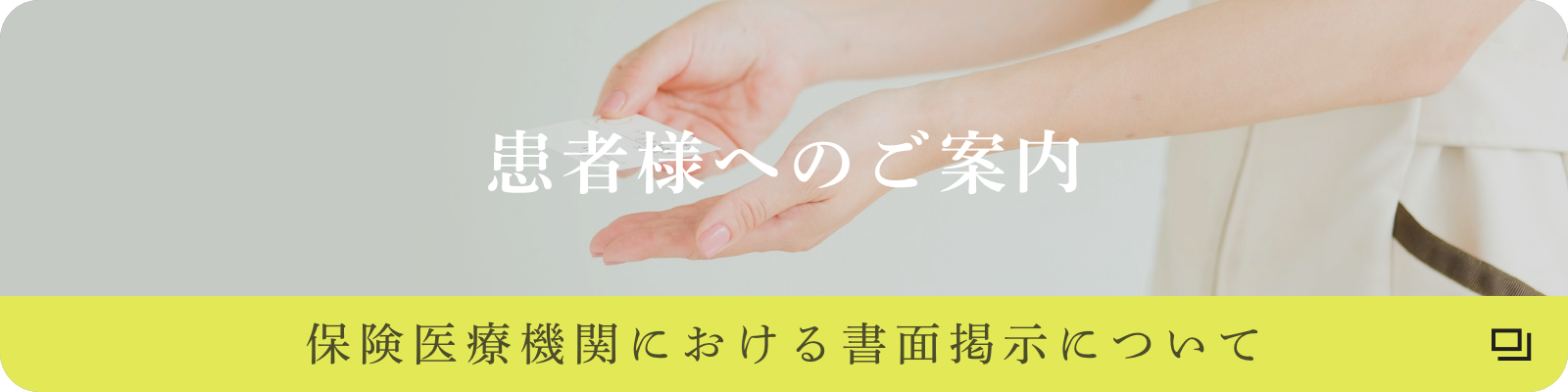お口ぽかんを放置しないで!子供の成長に与える影響と早期対策のススメ
◆はじめに
こんにちは。松原市・河内天美駅すぐの「たなか歯科クリニック」です。
お子さまのお口を見ていて「いつも口が開いているな…」と感じたことはありませんか?
この「お口ぽかん」は、成長過程ではよく見られる状態ですが、放置すると歯並びや健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、お口ぽかんを放置してはいけない理由と、早期対策の重要性について詳しく解説します。
◆お口ぽかんを放置するとどうなる?
歯並びの乱れ
お口ぽかんは舌の位置が低くなる「低位舌」と結びつきやすく、歯を内側から支える力が弱くなります。
その結果、
- 出っ歯(上顎前突)
- 歯列のデコボコ(叢生)
- 開咬(奥歯だけが当たり、前歯が閉じない)
といった不正咬合を引き起こすことがあります。
集中力の低下と学習への影響
口呼吸が続くと、脳への酸素供給が十分に行われず、集中力や持続力に影響します。学習意欲が続かない、すぐに疲れるといった傾向も見られることがあります。
感染症や虫歯リスクの増大
鼻呼吸ができないと、空気をろ過する鼻の機能を使えず、風邪やインフルエンザなどにかかりやすくなります。
さらに、口が乾燥しやすくなることで唾液の自浄作用が低下し、虫歯や歯周病、口臭のリスクが上がります。
◆早期に取り組むべき理由
成長期は改善のチャンス
お子さまは成長とともに顎や歯列が発育します。この時期に正しい呼吸習慣を身につけると、自然な顎の成長が促され、矯正治療の必要性を減らせる可能性があります。
習慣化を防ぐ
「お口ぽかん」が癖になると、大人になってからも口呼吸が習慣化してしまいます。早めに意識づけを行うことで、将来的なトラブルを予防できます。
小児矯正の効果を高める
すでに歯並びに影響が出ている場合でも、早期に小児矯正を始めることで負担を軽くし、より効果的に改善できます。
◆ご家庭でできる早期対策
鼻呼吸を意識させる
お子さまに「鼻から吸って鼻から吐く」呼吸を意識させましょう。就寝時に口が開いてしまう場合は、枕の高さや寝る姿勢を見直すことも大切です。
口周り・舌のトレーニング
- 舌を上あごにぴったりつけて「んー」と声を出す
- 風船を使って息を吐く練習をする
- ガムをよく噛んで顎や唇の筋肉を鍛える
これらは家庭でも楽しく取り組める簡単な方法です。
食事内容を工夫する
柔らかい食事が中心だと咀嚼筋が発達しません。根菜類や肉など、しっかり噛む必要のある食材を取り入れることをおすすめします。
◆歯歯科医院での早期対応
当院では、お子さまのお口ぽかんに対して以下のようなサポートを行っています。
- 口腔内チェック:歯並びや舌の位置を確認
- MFT(口腔筋機能療法)の指導:舌や口の周りの筋肉を鍛えるトレーニング
- 小児矯正の検討:必要に応じて矯正治療を提案
- 耳鼻科との連携:鼻づまりやアレルギーが原因の場合は耳鼻科での治療を併用
お子さま一人ひとりの状態に合わせて、無理のない方法をご提案いたします。
◆保護者が気をつけたいチェックリスト
- 食事中に口を閉じて噛んでいるか?
- テレビやゲーム中に口が開いていないか?
- 就寝時に口が開いていないか?
- 鼻づまりやいびきがないか?
こうした小さなサインを見逃さず、早めに相談することが大切です。
◆結論
お口ぽかんを「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、歯並び・発音・集中力・感染症リスクなど、多方面に影響を与えます。
しかし、成長期の早期対応によって改善のチャンスは大きく広がります。
たなか歯科クリニックでは、お子さまのお口の状態を丁寧に確認し、原因に合わせた改善策をご提案しています。
「うちの子は大丈夫かな?」と少しでも気になったときが、早期対策のベストタイミングです。ぜひお気軽にご相談ください。